|
20世紀もあと2日(年末のご挨拶)
 あと2日で私たちがそれぞれの感慨をもっている20世紀が終わります。私たちは、それぞれの20世紀を生きてきましたが、これを読んでいる人で22世紀をみる人はいないでしょう。そういった意味で、ミレニアムを迎えた昨年もそうでしたが、今年も歴史を振り返るということが普通の新年より強いのは当然だと思います。私も「世紀末のわが国の政治的虚空」と題して5回にわたり、現在のわが国の政治情勢をそれなりに分析してきました。こちらの方は、過去を振り返るというより21世紀の政治を考えるために現状を分析しようと思って書きはじめました。 あと2日で私たちがそれぞれの感慨をもっている20世紀が終わります。私たちは、それぞれの20世紀を生きてきましたが、これを読んでいる人で22世紀をみる人はいないでしょう。そういった意味で、ミレニアムを迎えた昨年もそうでしたが、今年も歴史を振り返るということが普通の新年より強いのは当然だと思います。私も「世紀末のわが国の政治的虚空」と題して5回にわたり、現在のわが国の政治情勢をそれなりに分析してきました。こちらの方は、過去を振り返るというより21世紀の政治を考えるために現状を分析しようと思って書きはじめました。
 最初は3~4回で終わるつもりでしたが、稿を進めていくうちに次から次と論及したいことがでてきて、まだ相当書かなければなりません。「世紀末のわが国の政治的虚空」と名づけたものですから、私は日本人的な律儀さでどうしても今年中に書き終えなければならないとおもっていたのですが、とても終わりそうもありません。年が明けても続けることにしました。どうかご了承ください。現在の政治状況を深く分析するなかから、21世紀において私たちが何をしなければならないかが明らかになってくるからです。 最初は3~4回で終わるつもりでしたが、稿を進めていくうちに次から次と論及したいことがでてきて、まだ相当書かなければなりません。「世紀末のわが国の政治的虚空」と名づけたものですから、私は日本人的な律儀さでどうしても今年中に書き終えなければならないとおもっていたのですが、とても終わりそうもありません。年が明けても続けることにしました。どうかご了承ください。現在の政治状況を深く分析するなかから、21世紀において私たちが何をしなければならないかが明らかになってくるからです。
 今年も白川サイトをご訪問・ご愛読をいただき、本当にありがとうございました。私が落選をした総選挙以後の半年だけでも10万余のアクセスをいただきました。さらに付け加えると、白川BBSは別サイトで常連の方々は直接こちらの方にアクセスしますので、これに約5万のアクセスがありました。あわせて15万のアクセスがあったということは、私にとって大きな励ましであると同時に感激でした。政治家にとって選挙での落選ということは死ぬよりつらいことですが、こんなことにめげず頑張らなければならないと思い、私の考えることを発信し続けてきました。それが私を支え、そのことにより私は政治家としての自覚を失なうことなく生きてくることができました。本当に感謝申し上げます。 今年も白川サイトをご訪問・ご愛読をいただき、本当にありがとうございました。私が落選をした総選挙以後の半年だけでも10万余のアクセスをいただきました。さらに付け加えると、白川BBSは別サイトで常連の方々は直接こちらの方にアクセスしますので、これに約5万のアクセスがありました。あわせて15万のアクセスがあったということは、私にとって大きな励ましであると同時に感激でした。政治家にとって選挙での落選ということは死ぬよりつらいことですが、こんなことにめげず頑張らなければならないと思い、私の考えることを発信し続けてきました。それが私を支え、そのことにより私は政治家としての自覚を失なうことなく生きてくることができました。本当に感謝申し上げます。
 20世紀も本当にあとわずかです。新しい年、新しい世紀がみなさんにとって素晴らしいものとなることを心からお祈り申し上げ、年末のご挨拶といたします。 20世紀も本当にあとわずかです。新しい年、新しい世紀がみなさんにとって素晴らしいものとなることを心からお祈り申し上げ、年末のご挨拶といたします。
09:00 上越市北城町の自宅にて 上越市北城町の自宅にて
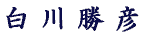
20世紀末のわが国の政治的虚空(その6)
<なぜリベラルでなければならないのか>
 これまでいろいろな角度から見てきたように、日本国民がいま現実に求める政治的理念
─
政治的価値観は、政治的にいえばリベラルであることは明らかです。 これまでいろいろな角度から見てきたように、日本国民がいま現実に求める政治的理念
─
政治的価値観は、政治的にいえばリベラルであることは明らかです。
 これは、国民自身がリベラルという言葉を知らなくともまた意識していなくても、政治的にいえばこうなるということです。リベラルということをもう一度きちんと定義しておきましょう。社会的公平を重視する自由主義のことです。セーフティ・ネットをきちんと整備している自由主義とです。 これは、国民自身がリベラルという言葉を知らなくともまた意識していなくても、政治的にいえばこうなるということです。リベラルということをもう一度きちんと定義しておきましょう。社会的公平を重視する自由主義のことです。セーフティ・ネットをきちんと整備している自由主義とです。
 現代の自由主義を大別すると、自由主義でいくけれどもこのように社会的公平やセーフティ・ネットを重視する考え方とあまりこのようなことを重視しない考え方があります。前者が現在ではリベラルとかリベラリズムと呼ばれ、後者が新保守主義と呼ばれています。しかし、どちらも自由主義であることはまぎれもないことであり、リベラルな自由主義を主張するか新保守主義と呼ばれる自由主義を主張するかは、その社会がおかれている状況によって決められることだと私は思っています。 現代の自由主義を大別すると、自由主義でいくけれどもこのように社会的公平やセーフティ・ネットを重視する考え方とあまりこのようなことを重視しない考え方があります。前者が現在ではリベラルとかリベラリズムと呼ばれ、後者が新保守主義と呼ばれています。しかし、どちらも自由主義であることはまぎれもないことであり、リベラルな自由主義を主張するか新保守主義と呼ばれる自由主義を主張するかは、その社会がおかれている状況によって決められることだと私は思っています。
 リベラルが主張する社会的公平や、そのためのセーフティ・ネットをあまりにも重視しすぎると、確かに自由主義であるかどうかも危うくなってくることもあります。イギリス病などと揶揄されたかつてのイギリスなどは、そうした例のひとつでしょう。サッチャー首相が新保守主義を果敢に掲げて、イギリスの大改革をやったのはそういう事情があったからです。アメリカにおいても、リベラルと称される勢力があまりにも放逸した怠惰な社会的動向があったため、またこれと期をいつにして長い不況が続いたために、レーガン大統領が新保守主義を掲げてアメリカの改革に果敢に挑戦しました。このふたつの新保守主義の改革は成功したと思います。 リベラルが主張する社会的公平や、そのためのセーフティ・ネットをあまりにも重視しすぎると、確かに自由主義であるかどうかも危うくなってくることもあります。イギリス病などと揶揄されたかつてのイギリスなどは、そうした例のひとつでしょう。サッチャー首相が新保守主義を果敢に掲げて、イギリスの大改革をやったのはそういう事情があったからです。アメリカにおいても、リベラルと称される勢力があまりにも放逸した怠惰な社会的動向があったため、またこれと期をいつにして長い不況が続いたために、レーガン大統領が新保守主義を掲げてアメリカの改革に果敢に挑戦しました。このふたつの新保守主義の改革は成功したと思います。
 日本でも新保守主義的な主張をする人もいますが、私は日本ではいま新保守主義的な動きはまだ必要ないし、歴史的にも日本の自由主義はまだそこまで成熟していないと考えています。もっと端的にいえば、いまわが国にある自由主義を阻害する要因は、そもそも自由主義以前の問題なのだと思っています。リベラルが主張する社会的公平やセーフティ・ネットは、いろいろな分野で自由化をしたところ、いろいろな弊害がでてきたためこれを何とかしなければならないとして実施されたものです。日本で問題になっている諸問題は、本当はまだ一度も自由化されていないということに最大の問題があるからです。自由化をしてみてはじめてどのようなセーフティ・ネットが必要か明らかになってきます。そしてそのセーフティ・ネットが度を越してしまった場合、これをどう見直すかが新保守主義の課題であったからです。 日本でも新保守主義的な主張をする人もいますが、私は日本ではいま新保守主義的な動きはまだ必要ないし、歴史的にも日本の自由主義はまだそこまで成熟していないと考えています。もっと端的にいえば、いまわが国にある自由主義を阻害する要因は、そもそも自由主義以前の問題なのだと思っています。リベラルが主張する社会的公平やセーフティ・ネットは、いろいろな分野で自由化をしたところ、いろいろな弊害がでてきたためこれを何とかしなければならないとして実施されたものです。日本で問題になっている諸問題は、本当はまだ一度も自由化されていないということに最大の問題があるからです。自由化をしてみてはじめてどのようなセーフティ・ネットが必要か明らかになってきます。そしてそのセーフティ・ネットが度を越してしまった場合、これをどう見直すかが新保守主義の課題であったからです。
 日本の政界でリベラルということがさかんに膾炙された1994~5(平成6~7)年ころ、当時社会党の救世主として期待されていた横路北海道知事(現衆議院議員・民主党副代表)が、あるテレビ番組で「社会的公平・社会的平等を重視する考えを、アメリカではリベラルといい、ヨーロッパでは社会民主主義というのだ」といっていました。これを聞いた私は、社会党のホープといわれている人でもこの程度の認識しかないのかと、率直なところ愕然としました。ヨーロッパでもアメリカでも、リベラリストが頑迷固陋な古典的自由主義者と戦って、いろいろなリベラルな制度を作ったのです。この人たちは、いずれも烈々たる戦う自由主義者でした。 日本の政界でリベラルということがさかんに膾炙された1994~5(平成6~7)年ころ、当時社会党の救世主として期待されていた横路北海道知事(現衆議院議員・民主党副代表)が、あるテレビ番組で「社会的公平・社会的平等を重視する考えを、アメリカではリベラルといい、ヨーロッパでは社会民主主義というのだ」といっていました。これを聞いた私は、社会党のホープといわれている人でもこの程度の認識しかないのかと、率直なところ愕然としました。ヨーロッパでもアメリカでも、リベラリストが頑迷固陋な古典的自由主義者と戦って、いろいろなリベラルな制度を作ったのです。この人たちは、いずれも烈々たる戦う自由主義者でした。
 自由主義や自由化政策は、その本来的性格からいってどうしても不平等をもたらします。それはある程度どうしようもないことです。多くの自由主義者は、そのようなことを仕方のないこととして考えたのですが、それに対してこの問題を何とかしなければならないと主張し戦ったのがリベラルといわれる勢力
─
リベラリストであったわけです。リベラリストが対峙した自由主義者を、私たちは現在では古典的自由主義者と呼んでいます。当時のリベラリストたちは、この人たちを保守主義者と呼んでいました。行き過ぎたリベラルな制度を見直して本来の姿にしようという主張をいま新保守主義と呼ぶのは、こんなところからきているのだと思います。 自由主義や自由化政策は、その本来的性格からいってどうしても不平等をもたらします。それはある程度どうしようもないことです。多くの自由主義者は、そのようなことを仕方のないこととして考えたのですが、それに対してこの問題を何とかしなければならないと主張し戦ったのがリベラルといわれる勢力
─
リベラリストであったわけです。リベラリストが対峙した自由主義者を、私たちは現在では古典的自由主義者と呼んでいます。当時のリベラリストたちは、この人たちを保守主義者と呼んでいました。行き過ぎたリベラルな制度を見直して本来の姿にしようという主張をいま新保守主義と呼ぶのは、こんなところからきているのだと思います。
 リベラリストたちは、自由主義の本来的矛盾である不平等という問題になぜ挑戦したのでしょうか。もちろん単純な正義感もあると思います。しかし、そうだとしたならば自由主義を諦めるしかありません。リベラリストが不平等を問題にしたのは、この問題を完全に放置していたのでは自由主義そのものが危うくなってくるという強い危機感だったと私は思っています。 リベラリストたちは、自由主義の本来的矛盾である不平等という問題になぜ挑戦したのでしょうか。もちろん単純な正義感もあると思います。しかし、そうだとしたならば自由主義を諦めるしかありません。リベラリストが不平等を問題にしたのは、この問題を完全に放置していたのでは自由主義そのものが危うくなってくるという強い危機感だったと私は思っています。
 国民が自由主義そのものを否定していなくとも、あまりにも不平等が大きくなった場合、政治的には自由主義はもたないからです。自由主義の本来的矛盾である不平等に、自由主義の本然の原則を守りながらこれが社会的な不公平にならないようにどうするか、これがリベラリストのテーマであり課題です。ただここで重要なことは、リベラリストたちは自由主義を否定はしていないということです。いや、熱烈な自由主義者であることです。熱烈な自由主義者であるがゆえに、自由主義を政治的に崩壊させるような不平等や不公平・不公正を看過しないところにリベラリストの真骨頂があります。このところを理解しないと横路さんみたいにリベラリズムも社会民主主義も一緒ということになってしまうのです。 国民が自由主義そのものを否定していなくとも、あまりにも不平等が大きくなった場合、政治的には自由主義はもたないからです。自由主義の本来的矛盾である不平等に、自由主義の本然の原則を守りながらこれが社会的な不公平にならないようにどうするか、これがリベラリストのテーマであり課題です。ただここで重要なことは、リベラリストたちは自由主義を否定はしていないということです。いや、熱烈な自由主義者であることです。熱烈な自由主義者であるがゆえに、自由主義を政治的に崩壊させるような不平等や不公平・不公正を看過しないところにリベラリストの真骨頂があります。このところを理解しないと横路さんみたいにリベラリズムも社会民主主義も一緒ということになってしまうのです。
 自由主義を否定せず、自由主義の本来的矛盾である不平等という不公平感をなくするということは、決して簡単なことではありません。いや、非常に難しいことです。しかし、リベラリストたちはこの困難な問題に果敢に挑戦してきました。そしてそれは可能なことでした。社会主義者や共産主義者が偽善だとか不可能だといってきたこの問題をなぜリベラリストたちは解決できたのでしょうか。 自由主義を否定せず、自由主義の本来的矛盾である不平等という不公平感をなくするということは、決して簡単なことではありません。いや、非常に難しいことです。しかし、リベラリストたちはこの困難な問題に果敢に挑戦してきました。そしてそれは可能なことでした。社会主義者や共産主義者が偽善だとか不可能だといってきたこの問題をなぜリベラリストたちは解決できたのでしょうか。
 それは、それぞれの国でやはり自由主義を支持する国民が多くいたからです。このことは、現在でも基本はまったく変わりありません。ソ連邦の崩壊ということに気を許して、自由主義が政治的に本来抱えているこの矛盾に目をつむると、自由主義体制に対する疑問や反対がいつ噴出してくるか分からないということを、自由主義者は決して忘れてはならないと私は考えています。 それは、それぞれの国でやはり自由主義を支持する国民が多くいたからです。このことは、現在でも基本はまったく変わりありません。ソ連邦の崩壊ということに気を許して、自由主義が政治的に本来抱えているこの矛盾に目をつむると、自由主義体制に対する疑問や反対がいつ噴出してくるか分からないということを、自由主義者は決して忘れてはならないと私は考えています。
(21世紀もつづけます) |
![]() HOME | NEWS | 略歴 | 著書 |
徒然草 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 旧サイト徒然草
HOME | NEWS | 略歴 | 著書 |
徒然草 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 旧サイト徒然草![]()
![]()
![]()