|
大世紀末の大政局観(その1)
 この「永田町徒然草」も、100号となりました。私としては100号である歴史的なことを書くつもりでいましたが、加藤元幹事長の政治行動でいま政局は大揺れとなっています。私のことは先に譲って、現在の政局について私の考えをのべます。 この「永田町徒然草」も、100号となりました。私としては100号である歴史的なことを書くつもりでいましたが、加藤元幹事長の政治行動でいま政局は大揺れとなっています。私のことは先に譲って、現在の政局について私の考えをのべます。
 加藤氏の政治行動をどうみるか、これは極めて大切なことです。首相の地位をめぐっての争いなら、それは自民党の中の単なる政局に過ぎません。しかし、自民党の幹事長を3期もつとめ、自民党の中の保守本流を自他ともに自認する宏池会の会長である加藤氏が、自民党的には禁じ手の今回のような行動をするはずがありません。加藤氏と20年以上にわたって政治行動を共にしてきた私ですから、そのことを誰よりも知っています。加藤氏の今回の政治行動は、もう少し大きな視点からみなければならないと思っています。 加藤氏の政治行動をどうみるか、これは極めて大切なことです。首相の地位をめぐっての争いなら、それは自民党の中の単なる政局に過ぎません。しかし、自民党の幹事長を3期もつとめ、自民党の中の保守本流を自他ともに自認する宏池会の会長である加藤氏が、自民党的には禁じ手の今回のような行動をするはずがありません。加藤氏と20年以上にわたって政治行動を共にしてきた私ですから、そのことを誰よりも知っています。加藤氏の今回の政治行動は、もう少し大きな視点からみなければならないと思っています。
 前号でも申し上げましたが、今回のことにつき、私はまだ加藤氏と話をしていませんし、当面会ってお話をするつもりもありません。加藤氏は、政治家加藤紘一として、考えに考え抜いた上での行動だと私は思います。加藤紘一という政治家は、一時の感情で軽率な行動をとる政治家ではありません。一方、私も総選挙で落選という厳しい結果を受けながらも、ひとりの政治家として「我いま何をなすべきか」、この数ヶ月間考え抜いてきました。そして、ひとつの結論に達したとき、時を同じくして加藤氏の今回の政治行動があったのです。 前号でも申し上げましたが、今回のことにつき、私はまだ加藤氏と話をしていませんし、当面会ってお話をするつもりもありません。加藤氏は、政治家加藤紘一として、考えに考え抜いた上での行動だと私は思います。加藤紘一という政治家は、一時の感情で軽率な行動をとる政治家ではありません。一方、私も総選挙で落選という厳しい結果を受けながらも、ひとりの政治家として「我いま何をなすべきか」、この数ヶ月間考え抜いてきました。そして、ひとつの結論に達したとき、時を同じくして加藤氏の今回の政治行動があったのです。
 それだけに、加藤氏の政治行動が何を意味するのか、誰よりも理解できますし、その決断に心から敬意を表します。いずれこのことはお話します。加藤氏の今回の政治行動をみるとき、自民党というものをどう考えるかということを抜きに、これを正しく理解することはできないと思います。これから先は、自民党についての私の考えです。いまの政局を考える参考にしてください。 それだけに、加藤氏の政治行動が何を意味するのか、誰よりも理解できますし、その決断に心から敬意を表します。いずれこのことはお話します。加藤氏の今回の政治行動をみるとき、自民党というものをどう考えるかということを抜きに、これを正しく理解することはできないと思います。これから先は、自民党についての私の考えです。いまの政局を考える参考にしてください。
 自民党は、その前身となる吉田自由党や鳩山民主党の時代を含め戦後50年余にわたって、政権党として日本の政治を担当してきました。自民党は、確かにいろいろと問題を起こしてきました。多くの疑獄事件もありました。また今日の日本にもいろいろな問題もあります。しかし、今日の日本ができあがるなかで、自民党がずっと政権党であったことは厳然たる事実であり、その意味で自民党にも功があったことは否定できない事実だと思います。自由民主党党員としては、功罪半ばするではなく功の方が大きかったといわせてもらいたいと思っていますが、 自民党は、その前身となる吉田自由党や鳩山民主党の時代を含め戦後50年余にわたって、政権党として日本の政治を担当してきました。自民党は、確かにいろいろと問題を起こしてきました。多くの疑獄事件もありました。また今日の日本にもいろいろな問題もあります。しかし、今日の日本ができあがるなかで、自民党がずっと政権党であったことは厳然たる事実であり、その意味で自民党にも功があったことは否定できない事実だと思います。自由民主党党員としては、功罪半ばするではなく功の方が大きかったといわせてもらいたいと思っていますが、
 20世紀を回顧するのではなく21世紀を展望するとき、果してこの自民党で日本の未来を切り拓くことができるのかが最大の問題意識でなければなりません。森首相やこれを支える四人組は、現在の自民党を論ずるときその問題点を象徴してくれるいい素材ではありますが、世間が問題にするほど重大視していません。自民党の本当の問題点は、実はもっと深く、大きいのです。 20世紀を回顧するのではなく21世紀を展望するとき、果してこの自民党で日本の未来を切り拓くことができるのかが最大の問題意識でなければなりません。森首相やこれを支える四人組は、現在の自民党を論ずるときその問題点を象徴してくれるいい素材ではありますが、世間が問題にするほど重大視していません。自民党の本当の問題点は、実はもっと深く、大きいのです。
 冷戦構造が崩壊したとき、自由主義陣営に立つということを標榜するだけでは自民党は存在価値を失ったのです。自民党としては、その時点で自民党の存在価値──政党としてのプリンシプル(主義・主張)を改めて国民に提示しなければならなかったのです。自由民主党という名前や歴史からして、それは当然のこととして自由主義ということになるわけですが、単に自由主義を標榜するだけでは十分でなく、自由主義の現代史的展開をしなければならなかったのです。しかし、それをするだけの人材や意識は、自民党という政党全体に残念ながらありませんでした。ほんのごく少数の者にしか、その危機感や問題意識はありませんでした。 冷戦構造が崩壊したとき、自由主義陣営に立つということを標榜するだけでは自民党は存在価値を失ったのです。自民党としては、その時点で自民党の存在価値──政党としてのプリンシプル(主義・主張)を改めて国民に提示しなければならなかったのです。自由民主党という名前や歴史からして、それは当然のこととして自由主義ということになるわけですが、単に自由主義を標榜するだけでは十分でなく、自由主義の現代史的展開をしなければならなかったのです。しかし、それをするだけの人材や意識は、自民党という政党全体に残念ながらありませんでした。ほんのごく少数の者にしか、その危機感や問題意識はありませんでした。
 自由主義の現代史的展開といった場合、二つの大きな潮流があります。新保守主義といわれるものと、リベラルといわれるものです。日本の現状を深く分析し、いったいどちらを日本の自由主義路線として選択するのか、これが自由主義の日本における現代史的展開の課題です。私は、リベラルなものを選択すべきであると考え、行動してきました。 自由主義の現代史的展開といった場合、二つの大きな潮流があります。新保守主義といわれるものと、リベラルといわれるものです。日本の現状を深く分析し、いったいどちらを日本の自由主義路線として選択するのか、これが自由主義の日本における現代史的展開の課題です。私は、リベラルなものを選択すべきであると考え、行動してきました。
 リベラルとは、「社会的公正を重視する自由主義」と私はいってきました。誤解を恐れずにもっと分かりやすくいえば、「社会的弱者に配慮する自由主義」ともいってきました。むきだしの自由主義ではないということです。新保守主義を私がとらない理由は、サッチャー首相やレーガン大統領が新保守主義を選択しなければならなかった事情は、幸いなことに日本にはまだないと考えるからです。イギリスは、イギリス病といわれるほど自由主義にとって深刻な事態がありました。アメリカでは、リベラルと呼ばれる人々がかなり問題のある現象を引き起こしていました。私は、日本にはそのような事情はまだないと考えます。 リベラルとは、「社会的公正を重視する自由主義」と私はいってきました。誤解を恐れずにもっと分かりやすくいえば、「社会的弱者に配慮する自由主義」ともいってきました。むきだしの自由主義ではないということです。新保守主義を私がとらない理由は、サッチャー首相やレーガン大統領が新保守主義を選択しなければならなかった事情は、幸いなことに日本にはまだないと考えるからです。イギリスは、イギリス病といわれるほど自由主義にとって深刻な事態がありました。アメリカでは、リベラルと呼ばれる人々がかなり問題のある現象を引き起こしていました。私は、日本にはそのような事情はまだないと考えます。
 1993(平成5)年6月の総選挙で、自民党は野党となりました。政権党であるがゆえに、自民党に群がっていた国会議員は、細川政権の異常な人気に恐れをなし、野党となった自民党を離党し、細川連立政権側にはしりました。11ヶ月で自民党は政権与党になりましたが、あの状態がもっと続いていれば、多分70~80人くらいは自民党を離党したのではないかと思います。そうしたならば、自民党はその後も政権党になることなどできなかったと思います。 1993(平成5)年6月の総選挙で、自民党は野党となりました。政権党であるがゆえに、自民党に群がっていた国会議員は、細川政権の異常な人気に恐れをなし、野党となった自民党を離党し、細川連立政権側にはしりました。11ヶ月で自民党は政権与党になりましたが、あの状態がもっと続いていれば、多分70~80人くらいは自民党を離党したのではないかと思います。そうしたならば、自民党はその後も政権党になることなどできなかったと思います。
 残念ながら、自民党という政党が良くも悪くも存立するためには、政権というものが必要不可欠なのです。ですから、私は自民党という政党をまもるために政権党になる努力をしなければならないと考えました。細川首相の1億円疑惑を追及するとともに、どうしたら自民党が政権党に復帰できるか考えた結果、可能性として考えたのが新党さきがけや日本新党や社会党との連立でした。 残念ながら、自民党という政党が良くも悪くも存立するためには、政権というものが必要不可欠なのです。ですから、私は自民党という政党をまもるために政権党になる努力をしなければならないと考えました。細川首相の1億円疑惑を追及するとともに、どうしたら自民党が政権党に復帰できるか考えた結果、可能性として考えたのが新党さきがけや日本新党や社会党との連立でした。
 細川連立与党内にいくら矛盾があるといっても、自民党が変わらずして自民党と連立を組んでもいいなどという政党が、現れてくれるはずがありません。私は、自民党がリベラルの路線を選択することを決断する絶好の機会だ考え、自民党内の同志を集める一方で、新党さけがけや日本新党や社会党の議員との接触を始めました。他党の議員からは、「自民党が本当にリベラルな路線を選択することなどできるのか」といわれました。しかし、それができなければ連立などできないのですから、自民党がリベラルな路線を選択することに私は自信をもっていました。 細川連立与党内にいくら矛盾があるといっても、自民党が変わらずして自民党と連立を組んでもいいなどという政党が、現れてくれるはずがありません。私は、自民党がリベラルの路線を選択することを決断する絶好の機会だ考え、自民党内の同志を集める一方で、新党さけがけや日本新党や社会党の議員との接触を始めました。他党の議員からは、「自民党が本当にリベラルな路線を選択することなどできるのか」といわれました。しかし、それができなければ連立などできないのですから、自民党がリベラルな路線を選択することに私は自信をもっていました。
 1994(平成6)年6月29日に村山内閣─自社さ連立政権ができたわけですが、これが可能となったのは、自民党がリベラル路線を選択したからです。村山首相のイニシャティブで、社会党が日米安保や自衛隊を合憲と認めるという路線変更をしただけではなく、自民党もこのとき大きな路線変更をしたのです。 1994(平成6)年6月29日に村山内閣─自社さ連立政権ができたわけですが、これが可能となったのは、自民党がリベラル路線を選択したからです。村山首相のイニシャティブで、社会党が日米安保や自衛隊を合憲と認めるという路線変更をしただけではなく、自民党もこのとき大きな路線変更をしたのです。
 自社さ連立政権下の自民党の政調会長を1期─幹事長を3期つとめた加藤氏は、誰よりもこのことを知っていました。私も自社さ連立政権を作った一人として、加藤氏を懸命に支えました。リベラルな路線を選択した自民党に対する評価は徐々に国民に理解され、自民党の支持も高くなってきました。小選挙区制のもとではじめて行われた平成8年10月の総選挙で、自民党が新進党に勝つということは、実は奇跡に近いようなことだったのです。 自社さ連立政権下の自民党の政調会長を1期─幹事長を3期つとめた加藤氏は、誰よりもこのことを知っていました。私も自社さ連立政権を作った一人として、加藤氏を懸命に支えました。リベラルな路線を選択した自民党に対する評価は徐々に国民に理解され、自民党の支持も高くなってきました。小選挙区制のもとではじめて行われた平成8年10月の総選挙で、自民党が新進党に勝つということは、実は奇跡に近いようなことだったのです。
 その選挙の参謀室長といわれる総務局長をつとめた私は、つくづくそう思っています。東京をはじめ都市部では、自民党の基礎票に対して新進党の基礎票は3~4倍ありました。定数が増えたこの都市部で勝たなければ、新進党に勝つことなど絶対に不可能なのです。この選挙の総指揮官であった加藤幹事長は、私以上にこのことを感じていたはずです。 その選挙の参謀室長といわれる総務局長をつとめた私は、つくづくそう思っています。東京をはじめ都市部では、自民党の基礎票に対して新進党の基礎票は3~4倍ありました。定数が増えたこの都市部で勝たなければ、新進党に勝つことなど絶対に不可能なのです。この選挙の総指揮官であった加藤幹事長は、私以上にこのことを感じていたはずです。
加藤幹事長は、リベラルな自民党をみごとにアピールし、総選挙を勝利に導きました。加藤氏は、愚直なまでにリベラルな路線を体現する政治家でした。手練手管は一切使いませんでした。その青臭さも国民の支持を受けました。政党にとっていちばん大切なことは、その党が掲げる理念であり、政策であり、生き方なのです。現在の自民党が国民から見放され始めたのは、この理念や政策や生き方を失ってしまったからです。そこにいちばんの理由があるのです。
 四人組と呼ばれている人たちは、ただそのことを象徴するにふさわしい人材だというだけで、自民党全体がそうなってしまったことに問題の本当の根源があるのです。このことが、今日の政局をみるいちばん大切な点です。 四人組と呼ばれている人たちは、ただそのことを象徴するにふさわしい人材だというだけで、自民党全体がそうなってしまったことに問題の本当の根源があるのです。このことが、今日の政局をみるいちばん大切な点です。
(つづく)
01:00 東京の寓居にて 東京の寓居にて
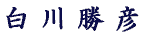
|
![]() HOME | NEWS | 略歴 | 著書 |
徒然草 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 旧サイト徒然草
HOME | NEWS | 略歴 | 著書 |
徒然草 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 旧サイト徒然草![]()

![]()
![]()